過去と未来が交錯する聖夜は、制御不能なBurning Christmas!
まさかまさかの前後編、ぼっちクリスマス回避のためにコタローが奮戦する、ぷにるアニメ第10話である。
というわけで全体的に今日も賑やか、大変明るく楽しい話なのだが、だからこそコタローの原点と現状が良く照らされていて、大変良かった。
第8話で案外クラく寂しいポジションにいることが明かされたコタローが、学校という社会であんまり位置を確保できてない現状が空振り加減に良く照らされ、そうなってる根源を探っていくと幼稚園時代の涙にたどり着くという…。
「男の子はかわいいの好きじゃいけない、”ズル”である」という、 無邪気で理由がないゆえに良く刺さる刃を、胸の一番柔らかな部分に突き刺されたコタローにとって、ぷにるという「カワイイトモダチ」がいてくれたことがどんだけ救いであったのか。
そしてその不定形の黄金期が、女の子の形を得てしまったぷにると性を意識するようになったコタローの現在に、どう残響しつつ変質しつつあるか。
そろそろ1クールの終幕が見えてくる中で、作品の中核にあるものを、しっかり捉え直す良いエピソードだなと思いました。
色んなモノが変わっていくし、深く刻まれた傷は早々簡単に消えないけども、そうしてたどり着いた場所には色んな連中がいて、賑やかで楽しい。
この話が”日常ラブコメ”である意味とありがたさが、しみじみ染みる回だったなぁと思う。
アニメでまとめて描かれてみると、ぷにるを連れて学校生活が賑やかになったことで、コタローの交友関係が広がりトモダチが増えた事を、メチャクチャ肯定的に描き続けてる作品なんよね。




というわけでクリスマスになると思い出す、コタローちゃん初めての涙から物語はスタートである。
客観的には指弾してる側の無邪気な容赦の無さ含め、「幼稚園によくある風景」なのだが、主観としては極めて致命的にシリアスで、だからこそそれに囚われてどこにも動けなくなることがないよう、普段は思い出さぬよう封じている、極めて重たい魂の鎖である。
幼稚園であっても社会は社会で、自分の外側にある価値観(例えば「男の子はかわいいことが好きであってはいけない」」 )を自分の内側に取り込み、それを自分の外側にいる他者へぶつけ、働きかけることで環境を変化させていく連続性が、そこには存在している。
幼いコタローちゃんは(おそらくここで初めて)自分の中にあるものが必ずしも、社会や他者に認められ、十全な自意識を満たしてくれる柔らかな素材ではなく、トゲトゲと自分を突き刺して涙させる、怖い存在であることを思い知らされた。
それは十数年たっても消えない、存在の根本を規定する魂の傷だ。
形而上核(魂)によって身体を自在に変化させうるぷにると、幼少期のトラウマによって可愛いものが好きな自分を”恥じ”だと感じ、それを私室の外側に持ち出せないコタローが、隣り合って主役をやっているのはとても面白い。
世の中学生の殆どがそうであるように、自分の中の思い込みと、外側にある押しつけが入り混じった、妄念の鎖に捉えられてまったく不自由なコタローに比べ、ぷにるは常に自由だ。
それはコタローが結構距離感に悩む、学校という社会組織との付き合い方もそうだし、自分が直感するカワイイをそのまんま造形して、世間の称賛を得てしまえるセンスにおいても言える。
コタローが出力する”好き”が、幼稚園のガキどもが殴りつけてくる”べき”の圧力を跳ね返すほどに本物であったのならば、ここまで彼も自意識こじらせていないだろう。
世間がどう思おうが、他人が何を言おうが、自分が好きだと信じるものは他人の心を揺り動かし、好きを広げていけるだけのパワーがあるのだと、自分の存在をあるがまま肯定できる。
しかしコタローにセンスはなく、それに引っ張られて得られるはずの外部の称賛、自己肯定感を生む成功体験も遠く、固く閉ざした外殻に自分の”好き”を閉じ込めていってしまうことになる。
そんな下向きのスパイラル、最初の一歩目が幼稚園での否定だったのだ。
ありふれた…だからこそ切実で致命的な自己否定の螺旋を、上向きに変えていくための足場はこの作品の内部、いくつか用意されている。
それはホネちゃん達との友情であったり、ぷにるというかけがえない存在であったり、きらら先輩への淡い慕情であったりするのだが、カワイイものを堂々好きと言える性別に立ち、御金賀家による(時に過剰な)社会的バックアップに支えられて、己の”好き”と/”好き”で戦うアリスちゃんとの関係は、結構大きいなと感じる。
現状コタローがあるがまま、キュティちゃんが好きな自分を出せるのは、ぷにるとアリスちゃんだけだからなぁ…。
その”好き”は、ヘンテコながら靭やかに二人を繋いでもいる。
第4話からの三部作で距離を縮め、第9話でマンガ金持ちなりの苦労を目の当たりにしたことで、アリスちゃんがかなり切実に苦悩し、彼女なり難しいものを飲み干しながら努力してる様子も、コタローは間近に見届けている。
それに影響されて”かっこいい自分”を求め、クソダセェ道のりへと踏み出しつつもあるという、正のフィードバックループが既に形成されているのは、過去の痛みに引きずられて”好き”を押し殺す方へと、自分を他者や世界から隠す道へと進みがちなコタローにとって、大事で幸せなことだ。
ぷにるとの特別な関係を大事にしつつ、こんな風に前に進む足場が多数用意されてるの、子どもが未来に進む事に真摯な作品だわな。




自分の”好き”が世界と他人に嘲笑われるかもしれないという、特大の痛みを叩き込まれたコタローちゃんは、その涙を受け止めたスライムが魂を宿す奇跡によって、特別なトモダチを手に入れた。
回想されるペンギンぷにるとの日々は、なにも自分を隠さなくて良いあるがままの心地よさに満ちていて、見ているだけで幸せになる。
そういう時代があってくれたこと(未だ続いていること)が、色々めんどくせー思春期へと進み出してしまったコタローにとってどんだけ救いであるか、コタロー自身は意識もしない。
その視野の狭い幸福が、まさに思春期という感じでもある。
ペンギンと子どもが戯れていると微笑ましい風景が、女の子と少年に形を変えるとやべー感じになってしまう、人間存在の不思議。
成長と性徴に伴うホルモンバランスの変化とも、身体的変化に付随する”あるべき自分”への社会的圧力とも無縁な、自由で無邪気なぷにるが気に留めないものに、コタローはガッチリ支配されてしまっている。
時を経ても、形が変わっても、何も変わらない関係性の核に素直になれば、頬を赤らめワーワー騒いで遠ざけることもないのに、どうしても気恥ずかしく、モヤモヤ変な気持ちが沸き上がってしまう。
その熱量ある歪みも、嘘ではなく確かにコタローの思春期にはあるのだ。
惨めさやら至らなさやら不器用やら、あるいは素直になれない臆病やら、シンプルな真実に目を向けきれない愚かさやら。
コタローの情けねぇ所も全部しっかり笑いに交え、確かにそこにあるのだと肯定してくれるこの作品の視線が僕はとても好きだが、同時にそれに引っ張られて本当に大事なものを手放してしまえば、過去から未来へと繋がっていくはずの縁も断ち切られてしまう。
それはなかなかのバッドエンドなわけで、ワーワー騒がしく思春期の身動ぎを繰り返しつつも、コタローは本当に大事なものを掴み取れる場所へと、彼自身の物語の主役らしく、ちゃんと進み出していく。
一人では絶対迷うので、色んな人の手を借りながら。
ここでぷにるの形に引っ張られて、ネトツイた性欲のるつぼに二人きり身を投げる性夜ルートを回避するべく、他人を家に呼んでクリスマスパーティーつう社会的活動に目を向けるのが、面白い運びだなぁと感じる。
それは私宅で行われるプライベートな行動でありながら、他者と世界に対して拓かれ、働きかけなければ成立しないパブリックな活動でもある。
小さな泡の中で自分を守っている子どもには出来ない、結構発達した自我を要求される一歩にコタローを押し出すのが、”キュティちゃんの絵本”つうのが好きだ。
誰かに”ズル”と言われようが、それが好きだと堂々いえなかろうが、コタローが好きだったものは、彼に道を示してくれる。
変化していくコタローの好きに影響されて、ぷにるがペンギンから女の子へと形を変えたのもそうなんだけど、ホビーを筆頭にした無生物が、人間からの”好き”に呼応し助けてくれる描写が多くあるのは、トモダチを描く物語としてとても豊かだ。
魂と自我を得たぷにるだけが子ども達の味方をしてくれるわけではなく、決まったプログラムで動くルンルーンも、物言わぬルンルやキュティちゃんも、コタロー達の未来がより善くなる助けを、さり気なく果たしてくれる。
ホビーでありながら児童でもあるぷにるが、ルンルーンというホビーをトモダチにして、幸せに楽しく生きてる描写が分厚いの、ホント好きなんだよなぁ…。




まぁそういう存在が、自分の欲望を反射して無邪気に女の子の形に変わり、ぺとぺと魅力的にアプローチしてくるからこそ、コタローも困っちゃうんだけどさ。
そういう難しさを遠ざけるためにも、コタローは立て看板持ってパーティーに人を誘い、トホホと失敗していく。
ぷにるという特別な存在に選ばれた人生の主役のようでいて、”好き”と”恥じ”を閉じ込めた私的な泡から出てこない、クラスの端っこにうずくまってるクラいヤツ。
学校という社会において、コタローのソーシャルアプローチは中々実を結ばない。
ここで陰キャらしからぬパーティーの誘いをおっ立てるのに、ぷにるが隣りにいなきゃダメ(あるいはそれが当たり前)なのが、コタローの現状を切り取ってて面白い。
勝手についてきて思うまま場をかき回し、なお皆の注目を集め愛されるぷにるを媒介にすることで、地味で目立たない(とクラスにおいて扱われてきた)コタローはホネちゃん達との繋がりを得た。
憧れのきらら先輩とも、ぷにるという児童を生贄に捧げることで興味を引き、その他大勢以上の存在感を突き刺すことに成功しているわけで、「面倒見てやんなきゃいけない弟分」というコタローの認識に反し、ぷにるこそがコタローを社会と繋げるアダプターになっている。
肥大化した自意識に目を塞がれ、こんがらがった欲望に迷わされてはいるものの、コタローの根っこは真っ直ぐで熱いヤツなので、距離が近づけばその善さも他人にちゃんと繋がるのだが。
”好き”を嗤われた傷に足踏みしてしまって、なかなか他人と繋がること、在るがままの自分を開示することに二の足踏んでしまうコタローの「外部化された自我」として、誰よりもコタローを知っているぷにるはコタローが本当にしたいことを外部に媒介し、手渡し、繋げていく。
それは得難いトモダチとしての代弁であるし、なーんも難しいこと考えぬまま”正解”を掴めてしまう、子どもの特権でもあるのだが。
そこら辺を手放しかけてるからこそ、コタローの思春期はギャフンな失敗まみれであり、トホホな後悔に満ちあふれているとも言える。
思い込みが激しく、自分の外にある客観的な事実をそのまま見れないくせに、完全に社会的に是認される価値観と自分を同一視し、普通に生きやすい自分を作れない矛盾が、コタローにはある。
自身過剰に己を求める社会や他者に翻弄されつつ、そこら辺上手く乗りこなして学園のマドンナやれているきらら先輩が、自分を置き去りにぷにるだけとよろしくやる身勝手(あるいは幼さ)を振り回す事はないのだが、コタローは温かで楽しいクリスマスの外側に、自分だけ置いてけぼりにされる妄想に翻弄されてしまう。
それはコレまでの体験が学習させた、彼の中だけにあり、だからこそ彼の中では確かに真実な痛みや惨めさが生み出し、補強し、行動に反映されてまた内的事実を強化していく、下向きの螺旋の戯画だ。
これがシャレにならない方向に行くと、とてもコロコロでは連載できない血腥き青春地獄絵図が展開されていくわけだが、この物語はコタローを捉える自意識の檻を、パワフルなギャグと温かな優しさでぶっ壊して、ありふれた閉塞から泣いてるガキを開放する方向へと、力強く進み出していく。
この上向きの跳躍に必要なエネルギーを確保するのに、”笑い”はうってつけの燃料であり、コロコロギャグの正統後継者である強みが出てるなと感じる。
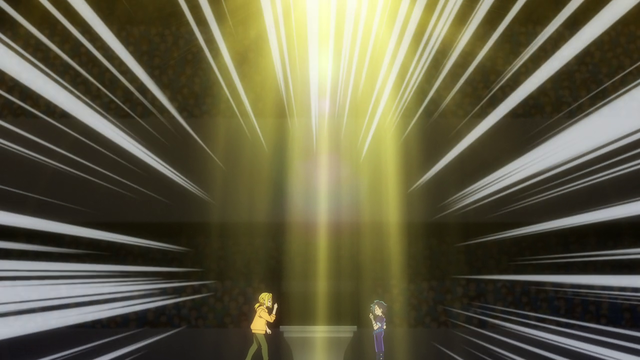



というわけで唐突に始まったホビアニだの、急なお嬢様ムーブだの、マッドサイエンティストにして児童の未来を考える善き教師のアプローチだの、色んな方向からクリスマスが燃え上がる!
ちょっとしか出番ねぇモンスーラ組が、斎賀くまい田村釘宮というあんまりにパワフル過ぎるメンバーで、かなりビビったりもする。
カノプスとポラリスのイメージバトルも作画気合入ってて、何処に力入れれば”文脈”を踏まえた笑いが生まれるのか、アニメ制作側がしっかり解って仕上げてくれている感じは大変嬉しい。
第8話で叙述トリック的に語られた「誰かの物語における脇役は、誰かの物語における主役」つう視座が、マジぷにると関係ないモンスーラ物語における南波くんが「主役たちに気さくに接してくれる、ちょっと年上の強豪」だと理解ることで補強されるのも、かなり好きな語り口だ。
モンスーラに全てを賭ける小学生達から見れば、いつまで経ってもコロコロキッズな南波くんは「年の離れた仲間」なわけで、クラスでの奇人っぷりとは違う顔を確かに持っている。
ぷにるを常に隣においたコタロー主役の物語が、自分の”好き”をブン回してメイド喫茶実現させたホネちゃん視点だと「一生モブ」なのと、響き合う視点よな…。
ずーっと一緒に暮らしてきたペンギンスライムが、女の子の形になった途端性欲に支配されたモンスターになってしまう恐怖と気恥ずかしさから逃れるためであっても、コタローは自分の閉じた私的領域から出て、サンタの装束でより広い場所に何かを求めた。
その結果が、一体何をもたらすのかは次回、パワフルな笑いを交えて描かれるだろう。
ワイワイ楽しく騒がしいクリスマスになりそうで、大変楽しみです。
ダサかろうがとりあえず行動してみるようになった、コタローの地道な成長が描かれてる回なんだが、結局引っ張りだこなのは彼ではなくぷにるって所に、徹底してありふれた惨めさ、社会への接続の難しさを抱えるキャラ性を感じて、「頑張れコタロー…」って気分になる。
まー今まで当たり前の社交性でクラスと繋がり得なかった、コンプレックスまみれのクラい少年が、簡単に爆モテ存在になんてなれねぇよな!
コタローは徹底的に中学二年生の等身大にふさわしく、世間にあるがまま求められるようなセンスがあってカワイイ”自分”というものを見つけて/取り戻してはいなくて、だからこそあるがまま自在に自分でいられるぷにるに救われ/支えられている。
そして奇跡のホビー生命体であり、人間に当然の成長から切り離されてるぷにるが得ることが出来ない当たり前を、ぷにるなりの社会性を交えて補給できる唯一の存在なのだ。
このお互いをかけがえないアダプターとしつつ、その特別さにどんな名前をつけたら良いのか手探りで迷っている二人の姿が、可愛くて素敵で、僕はいっとう好きなのだ。