獣の牙を甘い糖衣で覆い隠してくれなかった恋に、歓喜を込めてハンマーを振り下ろそう。
ちょっと調子くれた凡人に狼印のオーバーキルがぶっ刺さる、小市民シリーズ第16話である。
「秋もやります!」と半年前告げられて以来、ずっと待っていた回である。
原作に比べこしゃまっくれた内言が減り、ごくごくフツーに何者かになりたかった瓜野くんの思春期が鮮明になっても、小佐内さんの残忍で聡明な処刑を、月下に見つめるこの瞬間を、僕は心待ちにしてきた。
このアニメが彼女を描く筆、羊宮さんの少しかすれて低い声がなぞる小佐内ゆきの輪郭は、あまりに魅力的だったから、彼女の敗戦がどう描かれるかはずっと楽しみだった。
そう、敗戦である。
一年かけて小佐内さんは、自分に声かけてきた他愛もない愚者を、小市民の立場を素直に受け入れ、誰かの幸せを自分の幸せと受け入れられるような”いい人”には出来なかった。
その味に染まってもいいと思える甘さを、賢さも優しさも強さも足りてない(それが高校生の普通でもある)瓜野くんは滲ませてくれなかったし、特別さへの誘惑を警戒する彼女の忠言を、当然無視した。
それが先に痛い目見た、思春期敗残者からの忠告であったと気づくことが出来ないくらい、瓜野くんの知性は凡庸で鈍重だった。
その報いとして、彼は月下にプライドを粉砕され、世界と己への幻想を殺されていく。
その吠え面は大層見応えがあったが、高校入学以来結構本気で小市民になりたかった小佐内さんにとって、自分が復讐の血を啜る獣でしかないと決定的に思い知るこの処刑は、たいへん甘くてかつ苦い。
あの夏の破綻以来、恋に恋する乙女とやらを演じたいと願い、自分なり献身的に”彼女”やってみた挙げ句ここにたどり着いてしまうのは、自分を善き場所へと導いてくれなかったボンクラを選んでしまった/選ばれてしまった己のやるせなさと合わせて、パッと見より切ない終着だと思う。
仲丸さんとあの最悪な終わり方をし、今回堂島くんに決定的な一言を告げられた、小鳩くんとどっこいどっこいの終わりっぷりだ。
小佐内さんは瓜野くんに、名探偵気取るには知性と冷静と悪辣が足らないと告げる。
しかしそれがあっても二人は当たり前の幸せにたどり着けなかったし、そもそもお互いを大事にも出来なかった。
卓越した知性とやらで、小鳩くんの恋がどんな顛末を迎えたかは既に描かれているが、むしろ人間が人間として当たり前に幸せになる道を、瓜野くんに足りないものは塞ぎかねない。
まぁそれが欠落しているからって、無知ゆえの無垢とか、愚かさ故の純粋さとかを、無条件に手に入れられるわけじゃないってことも、瓜野くんの短くみすぼらしい青春に、しっかり綴られてきたわけだが。
この一年思春期を歩いた皆、それぞれの形でみんな最悪だ。
それでも夏の先に秋が続き、そこから更に冬の物語が綴られていく。
自分が最悪の獣で、憧れていた平凡にはたどり着けず、あるいは満足も出来ない性根を思い知らされてなお、変わり得ない自分を抱きしめた上で、凸凹ザラザラ肌触りの悪い青春は続いていってしまう。
そういう事実を飲み干すハラを固めたからこそ、小佐内さんは他愛もない彼女の彼氏をどう殺すか、凶器の選定から犯行のタイミングまで、獣の嗅覚を蘇らせてしっかり道を敷いた。
小鳩くんも受験勉強の傍ら、瓜野くんが認識すらできない事件の構造を俯瞰で見抜き、己が見たい絵図に引っ張れず客観的で、有効な罠を張り巡らせて事件を終わらせた。
一応中学時代に痛い目見て、ドヤ顔で推理晒すより大事なことが世の中にある(らしい)ことを、小鳩常悟朗は思い知っている。
それでも眼の前の人間の顔色見るより、”日常の謎”を弄んで己の頭脳を誇る誘惑に押し流されたから、仲丸さんとの恋はああも無惨に終わった。
狐は知恵働きの旨味を諦められないし、狼は奸智を駆使した復讐を捨てれない。
彼女から終わらせられるにしても、彼女が終わらせるにしても、二つの恋の終わりはそういう、人間もどきの本性を否応なく突きつける。
一年かけてこの結果、つくづく勝者などどこにもいない、青春泥沼撤退戦であった。
瓜野くんに甘い期待を寄せて、持ち前の苦みを恋で甘く染め上げていく計画は、結局上手く行かなかった。
瓜野くんにそういう器量が(名探偵の資質と同じく)なかったし、そういう存在に彼氏を導ける能力も、狼には欠けていた。
でも、多分意思はあったのだ。
世の中で疎まれず求められる、フツーの幸せを抱きしめられるフツーの人になってみたいという願いは、同盟が破綻してなお消えず…むしろそっちが壊れたからこそ、恋なるものに突破口を願う気持ちは強かったのかもしれない、と思う。
そういう祈りを形にするには、狐も狼も他者への敬意と共感に欠け、知恵に優れた己を誇る牙が尖すぎたわけだが。
こんだけ激烈なとどめを刺されてなお、瓜野くんのフツーな知性は一年付き合った女がどんだけの怪物であるか(そして物語を不自由なジュブナイルから変質させきるほどには、怪物になりきれないか)を、把握できない。
彼に解るのは、これまでそうであったように自分の欲望だけであり、それはまぁまぁ、高校生のスタンダードでもあろう。
しかしこの物語はそんなありふれた傲慢と優しくなさを、「よくある失敗だよね!」と励ましても、受け入れてもくれない。
極めて残酷に思春期の万能感をぶっ壊されて、よたよたよろめきながら月の遠さを…そこに手が届かない己の惨めさを、噛み締めながらどっかへ去っていくだけだ。
その無惨なよろめきが、小佐内犯人説を割と早い段階から排除しつつ、その執着を見届け己の推理が世界を救うさまを見届けるべく、色々画策し行動した小鳩くんの特別さを、際立たせるための道具なのか。
次回描かれる狐と狼、一年ぶりの対話に鮮明になってくるとは思うが、どういう描かれ方をしても二人共、根本的な所で既に負けてる印象はある。
望んだ自分にはなれなかった。
恋…というにはあまりに身勝手で優しくない何かは、自分を変えてはくれなかった。
どうしようもない獣を人間に変えてくれるほど、素敵で劇的な恋愛は彼らの青春には埋まっておらず、それを掘り返せる魂があるなら、そもそもこんな荒野にはたどり着いてない。
それでも、恋で変わってみたかった。
誰でも良かったけど彼女と選んだ相手が、何を望み何を求めているのか、何も理解らないまま微笑みを演じて、決定的にすれ違い間違っても。
なんとなくその手を取ってみて、早い段階で頭の回転の鈍さ、波長の合わなさに苦笑いを噛み殺していた男の子を、結局罪に問われない凶器でぶっ殺しても。
獣はこの一年、どうにか人間なるものになってみたかったのだ。
しかしまぁ、それは叶わない。
賢い獣が誰からも疎まれない、特別な世界を自分の周囲に広げて、”日常の謎”から超人ミステリへと作品ジャンルを変えてしまえるだけの特別さも、掴めはしない。
結局のところ二年半前、中学時代の傷からボタボタ赤い血を流しながら、微笑ましく慎ましやかな謎に一緒に笑い合って、甘味を前に青春を演じていた頃、抱えていた歪さに戻るだけ。
人のカタチを希いつつ、獣だけが通じ会える鋭いダイアログにお互いの知性を照らして、心地の良い切れ味で共鳴できた、あの時代に戻るだけ。
一つ違うのは、自分たちが”恋人”なるものすら本当には大事に出来ず、決定的にぶち壊しにしてなお、その破綻に引っ張られて思い悩み足を止めるような、人間味もまた持ち合わせていないと知ってることぐらいだ。
そこから新たに始めるのなら、物語は円環を辿って振り出しに戻るように見えて、螺旋に上昇…
あるいは獣同士お互いを満たし合う、クレバーな奈落に堕ちていくのだろう。
上がってんのか下がってんのか、正しいのか間違ってるのか。
なかなか判別が難しい落着点へと物語は突き進んでいくけど、僕が惹きつけられた、あの美しく無様な獣たちの眼光はいよいよヨルに冴えていて、大変いい感じだ。
その道中に付き合わされて、フツーの青春送ってりゃ衝突することもないメガトン級の致命打食らわされた瓜野くんは、誠にご愁傷様。
でもまぁ、身分不相応な高望みを、低劣で平凡な知性と品性で望むならこうなるって、いい勉強にはなったじゃないか。
月下によろめく青春の遺骸を前に、そう言えるほど僕も、優しくはない。




かくして物語は堂島くんが月光の下、タイトルに冠する”小市民”への死刑宣告を叩きつけるところから始まる。
仲丸さんと向き合う中、イヤってほど示されたぶっ壊れ方も、瓜野くんが空回りする中外野から放火事件の全容を暴き、解決への道筋を立てた知性にしても、そらー小市民には収まらない。
等に解りきっていた事実を告げる資格は、作中唯一最も正しい意味で”小市民”でいられる男以外にないのだろう。
結局狐も狼も、己の苦みを甘く包んで、痛みもなく平凡に生きていく道なんて辿れない。
彼らが進む道の先には、いつでも赤い炎が燃えているのだ。
そんな一つの終わりを小鳩くんが飲み干す時の表情が、事件解決の甘さを無化するくらいに切ない痛みに満ちてて、とても良かった。
気に食わない、反りも合わない相手のはずなのに、小鳩くんにそんな結論をしっかり告げてあげる堂島くんの律義さが、月下に冴える。
その色は甘ったるい夢を拒絶する冷たさに満ちてて、だから心地いい。
暗闇に燃える炎に惹かれて、一年ぶりの再開を果たす獣達の危うい色彩とは、ちょっと違った冷たさがある。
小鳩くんはハンマーを持たず、小佐内さんはタンクに手が届かない。
お互い足りないところを補い合って、こっからの決着をぶち壊しにする被害を止めた再会は、危うく魅力的な獣臭を纏う。
この決定機に瓜野くんは間に合わないし、仲丸さんはそもそもこういう場所に期待とすら思わない。
人非人の名探偵(未満)が、特別性の冴えた頭脳を持つからこそ交錯した、シャレになんない事件を終わらせるクリティカル・ポイント。
自分が犯人に手を伸ばさなくても、望んだとおり誰かが終わらせてくれる仕込みの巧さもひっくるめて、似た者同士のお互い様が、ようやっとたどり着くべき場所へたどり着いた。
そこに人命救助の色が少しあって、瓜野くんが己のエゴを満たすために平気で踏みつけにしたものを(形の上でも、成り行きの結果でも)大事にしているのは、残酷な皮肉だなぁと思う。
犯人を自分の手で捕まえて、白雪に特別な己の足跡を刻むよりも大事なことが、どうやら世界にはあるらしい。
小鳩くんと小佐内さんは既にそれを思い知ってて、その真の意味を(例えば堂島くんのようには)解らないけど、大事にしなきゃいけないらしいとは考える。
その結果この場所へたどり着き、自分たちのエゴを照らすために燃えてるわけじゃない、全く洒落にならないヤバい炎を、収めるための共同作業を頑張る。
その人間らしさを擬した行いは、獣なり知恵を正しく使おうとあがいた一つの到達点に見えて、無様で綺麗で微笑ましかった。
獣たちがここに行き着くしかないなら、ここから進み出すしかないのだろう。




まぁその前にしっかり始末をつけるべきものがあって、というかそれを刈り取るのは狼にとってあまりに大きな愉悦で、だから見過ごすことなんて出来ない。
甘いスイーツを口に運ぶのと同じくらい、心地よい破滅を手渡し、見届ける悦楽が闇の中待ってるとも知らず、瓜野くんは誘蛾灯に誘われて夜の公園へ流れ着く。
飛んで火に入る夏の虫、気づけば獣の口の中。
瓜野くんを誘い捉えるフェティッシュが、後に小鳩くんが舞台に上がるタイミングでは一切画面に映らないのが、凡人と名探偵(未満)、噛ませ犬と本命の残酷な格差を語っていてエグい。
瓜野くんと小佐内さんの一年間、その総決算となる今回、画面は犠牲者だけがそのヤバさに気づいていないホラーの色合いを、かつてないほどに強めている。
僕らがあの夏の日思い知った、狼の牙の鋭さにずーっと瓜野くんは気づいていなかったし、それが彼が今回殺されるしかない犠牲である、何よりの証明でもあった。
小佐内さんの知性と異常性を嗅ぎ分けられる鼻を持っているなら、そもそも放火事件を放置/解決して、己のアイデンティティを確立しようとするヤバさにも気付けただろうし、自分が運命を切り開く主役ではなく、操られるだけの傀儡だってこともうっすら見えた…かもしれない。
そうならなかったから、この処刑場である。

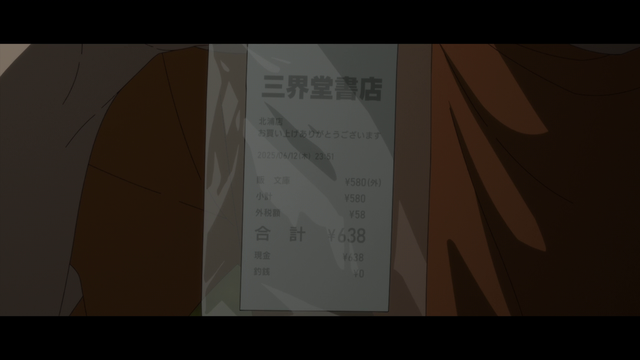


愚鈍であった罪、傲慢であった罪、平凡であった罪。
ドヤ顔で瓜野くんが綴る推理は、軒並み眼の前の女やら他の誰それやらに誘導された絵であり、それを導いた張本人は失笑を噛み殺しつつ、名探偵気取るボケカスを見つめる。
小佐内さんは獲物の首を落とす終局まで、瓜野くんと同じ地平には立たないし、彼が見据えている推理空間は小鳩くんのそれとは違って、現実…あるいは瓜野くんが現実だと思いたい、偏見と独断の塊しか展開しない。
遠く寂しく、澄んで美しいあの岸辺に立つためには、瓜野くんには知性の光が足りなすぎる。
それが解ってるから、小佐内さんは遊具を降りない。
思考の極限まで潜りうる、小鳩くんの資質に並び立ち、時に大胆な(大胆すぎる)行動力でそれを追い越しすらする小佐内さんにとって、想定通りの推理(未満)を垂れ流す恋人の言葉は、あまりに鈍重で冴えに欠けている。
脳髄を加速させ、ここではないどこかを確かに見せてくれる、特別な閃きを甘く味合わなければ、結局満足できない己を一年かけて思い知って、元彼相手に始末をつけてあげてる…とも言えるか。
瓜野くんは小佐内さんを甘く正しく人間らしく染めるシロップにも、知性が弾け少し苦い炭酸飲料にも、なれなかった。
水というには濁っていて、必須でも唯一でも絶対でもない、名前のつかない何かが、闇の中迷妄にのたくる。
自分がそうであってほしいと切望し、都合のいいヒントを繋ぎ合わせて自分だけの真実を描く、心地よい陶酔。
それに目を塞がれていては、誰かを都合よく動かして心地よい復讐を遂げることも、客観的に真実を見破ってドヤ顔することも出来ないと、獣たちは良く知っている。
そこである種の謙虚さを手に入れておくことが、探偵業のスタートラインだと、小佐内さんは極めて分かりにくいサインでもって、かつて恋人に伝えようとはした。
それを受信できるセンスも人品も、フツーの高校生たる瓜野くんには、当たり前に無かったわけだが。
まぁ、ガキなんてそんなもんじゃん?




…で軟着陸させては、身の程を思い知って絶望し、誘われ操られて火にあぶられる愚者を、味わうことは出来ない。
小佐内さんはさんざん思考誘導し、この未熟な推理をその口から吐き出させるよう、透明な糸で引っ張ってきた獲物の首を、ようやく絞める。
瓜野くんが狼を殺す銀の弾丸だと思っていたものは、軒並み獣自身がわざと開けた思考経路でしかなく、ノセられ嗤われているかもしれないと思いもしない/思いたくないボンクラは、その糸の存在すら気づくことなく、携帯電話を確かめるタイミングすら操作されていく。
今この結末にだけ、傀儡繰りの糸が伸びてたわけじゃない。
ずっとこの二人はそういう繋がりだったし、小佐内さんも望んでいた甘く幸せな平凡に引っ張っていくよりも、愚かしい誤謬と約束された破綻へと導く方が、小佐内ゆきには上手くいくって話でもある。
…逆にいうと、結構真面目に恋して変わろうとあがいてみたけど巧く出来ず、いざ相手を破滅させようとするとあっという間に舞台が整ってしまう、小佐内ゆきの壊れ方を明示する処刑場ともいえる。
ここら辺、知より情を大事にしたかった仲丸さんと同じ星には住めず、”日常の謎”を舌の上で転がす遠い星から出ようとしなかった/出れなかった、小鳩くんの恋とやっぱ似ている。
バカを殺してスカッと爽快…勝利に見えるものは、やっぱひたすら無惨な敗北だ。
小佐内さんは瓜野くんが無自覚にガバガバ開けた付け入る隙を、全部指摘して刺し殺しに行く。
自分が特別な存在だと思いたいから、他人の知性や興味を軽んじて本気にならず、疑いもしない。
そうやって突き刺す言葉の刃は、結局他人を大事にできない、知ることと読むことしか出来ないミステリ読者の権化にもそのまんま帰ってきて、賢い小佐内さんは(あと影で聞いてる小鳩くんも)その痛さに、結構自覚的だと思う。
そんな二人が曲りなり、敬意に似たものを取り繕って、心地よく繋がりちったぁ大事にできる、破綻した次善。
この愚者への青春処刑は、そんな歪な双星の瞬きを、確認するための儀式でもある。




というわけでさらば彼ピッピ!
あんたエゴイズムだけが肥大化して周りも自分も見えておらず、優しくも賢くも鋭くもない、獣未満の何かだったよ!
瓜野くんの根本が、自分が特別でないと思い知ってるからこそ特別な自分を信じたい、極めて小市民的な願望にあると良く知っているから、小佐内さんは彼を特別だと思い込ませた全部が、自分の仕込みであると告げる。
獣の本性も見抜けず、守るべき小さな女だと見下していた相手が、自分のプライドを守るために密やかに、賢く、自分の世界を操っていた事実。
それが、瓜野くんが信じたかった輝きを奪っていく。
見上げる月は孤独で、酷く遠い。
最初から、そんなもんだと思っていた。
瓜野くんを決定的に殺す微笑みは、ナチュラルにあらゆる他人をナメてる狼にとって、紛れもない真実だろう。
同時にそんなんじゃない特別が、自分を恋の相手と選んだ少年にあってほしいと…それを通じて変わってみたいと、願ったのも本当だと思う。
まぁ瓜野くんがこーで小佐内さんがあーだった結果、結果としてこの惨殺処刑に至ったわけだが、叶わなかったからといってその祈りが、存在しなかったわけじゃない。
そんなモノがあったからといって、世界が正しく進み獣が人間になれるわけでもないし、結局そんな願いで自分も世界も変わってくれないと、諦め学ぶ一年間だったけど。
小佐内さんは、殺すべきと認識した相手には容赦がないし、油断もない。
自分に動員できる知恵と影響力を全て駆使して、一番理想の形に皿を整え、復讐の甘い蜜を搾り取る。
瓜野くんは結局、そういう獲物として認識されてしまったわけだが、では一年前からこの決着を待ち望み、雌伏の時を重ねてここにたどり着いたのか?
ここら辺の謎解きは、ヨタヨタ退場していったボケカス噛ませ犬の後、本命名探偵登場によって掘り下げられて行く部分だ。
人非人は人非人をよく知る。
お互い、恋にそれなりに頑張った一年間がこうも挫滅して、「背伸びた?」以上のお話しもたっぷりあるだろう。
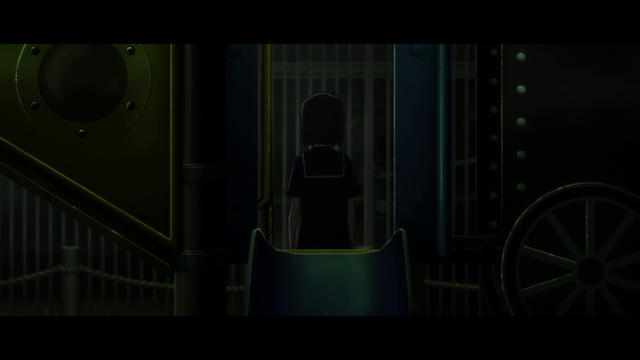
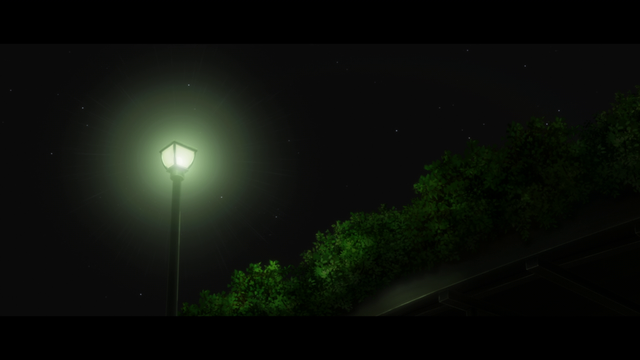


結局お互いの隣に戻ってくるしかない、この物語の主役たち、最後の舞台。
そこにたどり着く時、瓜野くんと違って小鳩くんは誘蛾灯に誘われないし、檻にも閉じ込められないし、捕食者と獲物にクッキリと分けられた上下に隔たれもしない。
何も見えていないし、事件解決のために様々なファクターを誘導も出来ない、名探偵未満とはそもそも、立ってる場所が違うのだ。
その高みが、小鳩常悟朗を人間らしくなんても、正しくも、幸せにもしないことは、既に描かれたとおりである。
あるいはここでもう一人の獣を待ち望んでいた、小佐内ゆきも同様か。
あの夏の終わりから、僕はこの再開を心待ちにしてきた。
二人がもう一度向かい合って、今度はかけがえない何かとしてお互い見つめ合って、繋がり直す瞬間を。
でもそこに至る道程で、イヤってほど描かれたのは彼らがどうしようもなく最悪で、他人に優しくも、フツーに正しくもなれない、残酷な歪さだった。
今回散々に踊ってぶっ飛ばされた瓜野くん(あと随分最悪だった仲丸さん)は、そんな最悪ニンゲンモドキが作品の真ん中に座る特別さを、照らすためのライトでしかないのか。
ここら辺、秋をやり切るには時間が余り過ぎ、冬を新たに綴るには尺がなさすぎるこのお話が、どう転がるかで、現れ方が変わってくるだろう。
瓜野くんが見事に名探偵になり損ない、ボッコボコにされて舞台から退場したことで、推理の最後を飾る二人が”正しい”ような錯覚を、このアニメは浮かび上がらせつつある。
でもそれは生存者バイアスでしかなく、思い返せば二人共大概に最悪である。
そんな最悪を思い知る一年間で、2匹の獣は結構切実に、フツーでマトモになってみたかったんだと思う。
それが叶わなかったんだから、獣が愚かな少年の思春期を食い荒らした今回は、やっぱ勝者無き敗戦なんだと感じる。
そしてそんな無様な決着にたどり着いても、謎に満ちた日常は続いてしまう。
その残酷でかすかな救いを、どう書くつもりか…次回もとても楽しみだ。