懐旧に魅入られて魔境に迷い、友愛に導かれて幽冥を旅立つ。
シャオヘイと楊明が九龍イチ抜けぴを決める、九龍ジェネリックロマンス第11話である。
工藤の後悔を中核に据えた第二九龍の構造とか、彼の認識が世界を形作るルールとかが明らかになってきて、いよいよあの蜃気楼に窓わされた人たちの物語も、終わりが始まった。
見るだけで苦しかったかつての”好き”を、間違いなく幻だが確かに存在もしているかつての己に抱きしめられて、シャオヘイは堂々と後悔にサヨナラを告げる。
それに同行する形で、楊明も令子の生き様に相乗りするのではなく、自分の足で母と向き合う決意を決めて、砂塵の瓦礫へ踏み出した。
人々があるべき現実に帰る度、蜃気楼の中でしか在られない令子は思い出の中孤独になっていく。
そんな残酷が顕になる中で、この街を成り立たせている工藤は何を思い、何に縛られ、どんな苦しみを軽薄な笑顔の奥に覆い隠しているのか。
やっぱそこら辺を暴かねば、終わるものも終われないな…という気持ちを強くする、見事な脇役の退場回であった。
二人が第二九龍を去る隣、ずーっと部外者だったユウロンがみゆきちゃんとの過去を濃厚に描き、共に血を流し復讐の沼に飛び込んだ同志として、あの人の後悔に当事者として切り込んでいくの、良い対比だなぁ…。
永遠の夏は相変わらず眩しいのに、真実が顕になるほどに、影の重さばかりが濃くなるね…。




というわけでアバンで短くド濃厚、ユウロンが抱え込んだ感情と因縁がぶっ放される。
令子への淀んだ殺害依頼を見ると”悪役”に位置づけたくなる彼だが、恋人よりも早くみゆきちゃんの隣りにいた幼馴染として、凄く冷静な判断力と重たい愛着が同居しており、そういう切り分けはもー出来ない。
共犯者として蛇沼みゆきの全てを知る彼の物語は、中々自分の内側を教えてくれない強がりボーイの過去を伝えてくれて、見ごたえと切なさがある。
お母さんの遺骸を前に復讐を誓うときの、修羅の形相を爬虫類の体温で覆い隠して、必死に立ってるんだなぁ…。
蛇沼への忠誠を、肌を刺青で汚されることで示した親友と並び立つために、己を傷つけ痛みを共有するユウロンの血は赤い。
この愛ゆえに状況を俯瞰で見通し、事件全体を解析する陰謀の装置であることを、己に任じて感じもある。
それは第二九龍という幻に、存在する価値を見出さない冷徹を彼に与えるが、そんな彼も砂塵の向こう側、蛇沼みゆきへの後悔を触媒に、生きたノスタルジーの中に飛び込む権利を得る。
ユウロンが安全圏を出て舞台に上がる理由が、憤怒と懐旧に引きずられていく親友を止められない後悔なの、ようやっと二人の地金が見えた感じがして良かった。
この暗く重たい感情、令子には滲み出せないモンだからなぁ…。
シャオヘイと楊明が連れ立って第二九龍を出ていく今回の後、自分とみゆきちゃんを繋ぐ絆、それを軋ませる痛みと後悔を認識したユウロンが、どういう行動に出るかは解らない。
グエンくんが顔を厳しく引き締めながら突き出す、幻の中の救いをもっと冷たく睨みつけている気配はあるし、愛が凶暴な形に尖る危うさもビリビリ漂わせているが、同時に彼を突き動かす親友への愛は、赤い血を宿す本物だと思う。
…冷静なフリしてかなり九龍に飲まれている、みゆきちゃんの動向次第かなぁ…。
となるとグエンくんがみゆきちゃんとどう再開するか、彼の心残りである工藤の行く末とも絡んで、色々揺れ動きそうだね。




さて来るものあれば去るものあり…幽霊都市の内部に身を置く人は、オリジナルの九龍には存在し得ない携帯電話で繋がり響き合う。
一人考え込むと、暗い淵に沈みそうな魔力がある九龍の影を、打ち払うように電話のコール音が鳴って、みんなが自分の大事な人を思い出す展開が連続していくのは、とても面白かった。
元々誰かと誰かが出会い、その声を聞いて己を変えていく交流をすごく大事にしている作品なので、いよいよクライマックスに差し掛かったこのタイミング、存在するはずもない未来のコミュニケーションツールが物語を牽引するのは、興味深い描写だ。
頑なに九龍の食事を取らないグエンくんは、その厳しさだけでは向き合えない工藤からのコールを受け取る。
令子への情に流され、自分が真実あるべき場所が見えにくくなっている楊明は、そんな親友が工藤の庇護から離れ、危険な北エリアに真実を探りに行く決意を聞く。
そしてシャオヘイは過去と現在、夢想と現実、善と悪が入り交じる複雑な場所で、一瞬目の前に生きるものを我欲に殺す影に取り憑かれかけて、かつての自分自身からの連絡によって目を覚ます。
群像を捕らえる迷いやゆらぎは、誰かが隣りにいてくれるからこそ立ち止まらず別の場所へ進み出して、淀んだ思考を打ち払っていく。
それを与えてくれる特別な機械が、”オリジナル”に存在していたのかいなかったのかは、最初からジェネリックであることを恥じず蔑さない…むしろ慈しむこのお話においては、大して大事ではないのだろう。
この軽妙な無節操(あるいは過度にオリジナルであることへの叛逆)が、凄くこのお話しらしくていいなぁと思うのだ。
シャオヘイが令子と出会ったとき、凄く邪悪な影に囚われるのが、僕は良かったなと思う。
それはこの幻の中確かに生きている、もう取り返せない愛しさをどれだけ大事にしているかを、他人を踏みじることも辞さない黒さで告げている。
でもそんな加害性だけが愛を証明するものではないと、他でもない令子とその友達…あるいはかつての自分自身に教えられていたから、シャオヘイはしっかりと迷って、光の方へと(あるいはちょっとギャグっぽい崩し顔が許される場所へと)進み出していく。
この明暗のゆらぎは、凄く人間らしくて好きだ。
影ではなく光を、過去ではなく未来を、シャオヘイが選べたことも含めて。



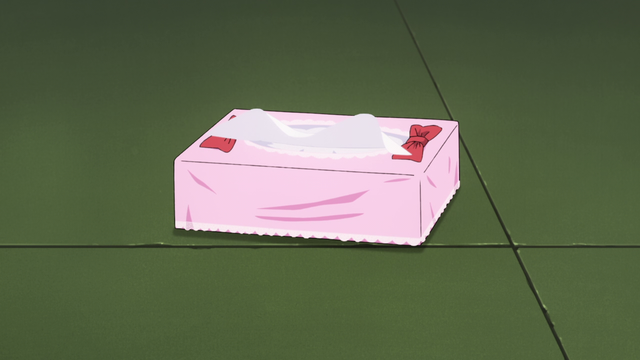
携帯電話が繋いだ奇縁によって、シャオヘイは三年前の自分と出会い直し、グエンくんは工藤とようやく対面する。
2つの出逢いが並走することで、第二九龍という幻の中核に工藤がいること…彼の認識が存在していなかった野良猫の宿を作り出し、三年前のシャオヘイを消す様子が描かれる。
世界の在りようを決める、神の如き立場に座りつつ、工藤発は凄く落ち着いていて彼らしく、正気に見える。
その平静こそが、愛する人と死に別れた後悔と痛みがどんだけ深く、彼をノスタルジーに縛り付けているかの、証明のようにも思えた。
三年前のシャオヘイの消滅は、迷いの中にいた現在のシャオヘイの道を決定的に決める。
そこで消えてしまったもの(消滅という既定事項に帰還したもの)も、消えないもの(かつての己が素敵だと褒めてくれたレース)も、真実の一欠片でしか無い。
歪で奇妙に、他人の懐旧や後悔を吸い込みながら成立している危うい幻に救いを求めることが、あり得ない夢だとシャオヘイにも解っていた。
解っていても奇跡をチラつかされて迷い、一瞬殺意の影に取り込まれかけ、しかし確かに時は過ぎ去り何もかもが変化し、しかし消え去らないものが確かにあることを、ここで認めたのだ。
それは凄く人間味のある、良い迷い道だ。
可愛いティッシュケースだけが遺品として残る部屋は、あまりに残酷で痛ましいけども、永遠の夏を繰り返す九龍の外に出てみれば、その無惨こそが真実…の、一つの形だ。
そこに消えても消えないものが確かにあるからこそ、シャオヘイも楊明も優しい夢から外へ出いていく。
それは客観的にみれば凄く正しいことで、でも何かを置き去りに切り離す寂しい旅立ちでもあって、その両方が今回、力強く匂い立っていた。
そのどちらかだけを世界の真実にしてしまわなければいけないと、思い込んでいた人たちが鎖から解き放たれて、より正しい場所へとたどり着く決着が、そろそろ近いのだろう。
そんな正しい目覚めが、第二九龍の眠れる神たる工藤発に訪れるのかが、また難しいところなのだが…。
繰り返すこの夏に身を置く限り、鯨井令子の命日は訪れない。
かつての自分が目の前で消え去り、だからこそ教えてもらった消え去らない”好き”を抱えて旅立っていくシャオヘイが、その長身に背負う決意はどうも、未だ工藤には遠く思える。
この距離を埋めて、歪さを認識しつつ夢の外へ出ないことを選んでいる工藤の、心の本当にたどり着く道のりは、もうちょい長そうだ。
だからこそ令子は、禁じられてた危うい場所、ドラッグや犯罪が匂うもう一つの九龍に踏み込んで、鯨井Bとこの街の真実を自分の目で確かめようとしてる。
工藤のため鯨井Bのため、何よりも自分自身のために、もっと強い自分であろうとしているのだ。
その貪欲で前向きな克己心が、俺は凄く好きだ。




そんな健気な令子を置いて、親友二人が霊廟を出ていく。
楊明がシャオヘイを蛇沼から守るために、令子の側から離れる決断をするの、強くて切なくて好きだ。
”本当の自分”を教えてくれた令子への依存を断ち切り、令子の影ではなく自分自身になることを選んだとき、あんだけ逃げていた母の懐に入ることを、楊明はためらわない。
この子も誰かのため自分のため、もっと強くなろうとしている。
その靭やかな決意に助けられて、シャオヘイは思い出の中置き去りにしようとしていた己の”好き”を、葬ることなく現実へと持ち出す。
冥界の衣が現世で消滅しても、それが確かに伝えてくれた手触りを慈しむシャオヘイの姿に、報いるようにピンクのレースは消えない。
この小粋な奇跡は、令子が令子のまま第二九龍を抜け出せる可能性に希望を残すが、しかし後悔を力強く断ち切れたからこそ、二人の視界にもう幽霊街は映らない。
砂塵に閉ざされた影の中、一人佇む令子の姿が切ない。
すぐに帰ってくると告げて進み出し、親友との予期せぬ永訣に呆然とする二人の姿も、また切ない。
旅立つことは、すなわちお別れでもあるのだ。
離別に宿る寂しさと決意、誇らしさと痛みを、シャオヘイと楊明が共に響き合いながら、九龍を巣立つ姿に刻みつけるエピソードでした。
幽霊街を成り立たせている色んな真実が顕になり、それに伴ってそれぞれの本当の願い、それに向き合うために果たすべき決断も見えてきて、いよいよクライマックスという感じがあります。
鯨井Bの死に蛇沼の遺産が関わってるっぽい事も解って、色んなピースが繋がってきたし、令子は楊明が隣りにいなくてもその闇に飛び込む勇気を、堂々掲げている。
そういう風に世界がうねる中で、一人工藤発だけがどこにも行かず、己を語らない。
それは…とても寂しいことだと思う。
でもロマンスとミステリをSFに絡めて同時展開するこの物語、工藤という異常現象の中枢を”解いた”ら、話が収まるのは面白いなぁと思った。
彼が鯨井Bへの弔意とか令子への思いとか、ヘラヘラ顔の奥心に秘めているものを全部吐き出せたら…そうなれる関係と強さへ令子がたどり着けたら、このロマンス(32歳のジュブナイルでもある)は終わりだ。
ようやく流れた涙と一緒に、蜃気楼の街も本来あるべき形へ戻るのだろう。
そう出来るだけの強さを求めて、令子は九龍のより暗い場所に踏み出していって、工藤はひまわりに呪われて動けない。
この前進と静止が、お話をどこへ連れて行くのか。
最終盤に差し掛かってもサスペンスが衰えず、次回も大変楽しみです!